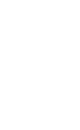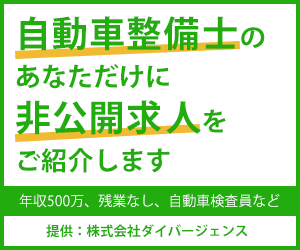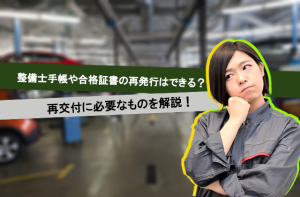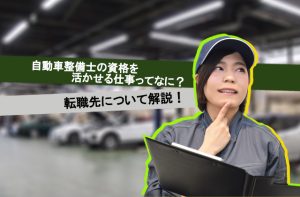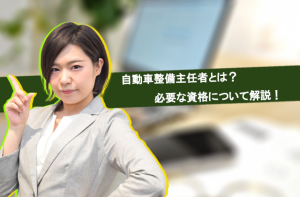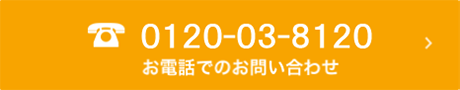自動車整備士に必要な資格の基礎知識

自動車整備士は、自動車の整備や点検、修理などを行う仕事です。整備士として働いていくためには、資格が必要となります。基礎知識として、自動車整備士の資格には種類があり、場合によっては複数の資格を取得しておくと就職や転職時に有利です。
まず自動車整備士は3級整備士・2級整備士・1級整備士・特殊整備士の4種類があり、その中でもさらに整備できる分野によって区分されています。2級・3級整備士はガソリン・ジーゼル・シャシ・二輪の4つ、1級整備士は小型・大型・二輪の3つ、特殊整備士は電気装置・車体・タイヤの3つに分けられます。
整備士をするならどの資格を取ればいい?
自動車整備士として働く場合、最低限必要なのは3級自動車整備士です。しかし、3級の資格ではできないことが多く、ほとんどの整備をするには2級自動車整備士資格が必要となります。
例えば、ジーゼル自動車整備士は、ディーゼル車とも呼ばれるジーゼルエンジンで動く自動車の整備などができる資格です。3級自動車ジーゼル・エンジン整備士では、エンジンなどの基本整備しか行えません。そのため、十分に整備するには2級ジーゼル自動車整備士の資格が必要となります。
ジーゼル自動車整備士と同様に、ガソリン自動車整備士ではガソリンで動く自動車を整備できますが、2級でなければ殆どの整備を行うことができません。
現在3級しか持っていない場合は、2級まで取得してしまえば多くの自動車整備工場で活躍できるので、取得を目指すことをおすすめします。また、2級整備士取得後に企業から選任されて研修を受けることで、自動車整備主任者になることが可能ですので、キャリアアップにも役立ちます。
必須ではありませんが、自動車整備士資格に加えて取得するとアピールに繋がるのは特殊整備士です。特殊整備士は1級・2級・3級の資格のように、持っていなければできない業務はありませんが、ある分野の専門知識や整備技術を持っていることを客観的に示せるため、転職などで有利になります。
資格がないと働けない?
それでは、3級以上の整備士資格を持っていないと整備工場で働けないのでしょうか?それは違います。その証拠に、整備士資格を取る方法の一つとして、整備工場などで整備の実務経験を積んでから受験する方法があります。
しかし、資格がないと整備補助など見習いとしての仕事しかできませんので、長期的に見ると3級以上の資格を取得するべきと言えるでしょう。
特殊整備士とは?

前の章にもある通り、特殊整備士には自動車電気装置整備士、自動車車体整備士、自動車タイヤ整備士の3種類があります。これらは名前の通り、バッテリーや自動ブレーキなどの電気装置の専門的な整備知識を持つ資格、車体やフレームの専門的な整備知識を持つ資格、タイヤについての専門的な整備知識を持つ資格です。
電気装置・車体・タイヤの整備自体は、特殊整備士の資格を持っていなくても自動車整備士資格があれば可能です。ですが、特殊整備士資格があれば、資格を取得できるだけの知識や技術を持っているという証になります。
自動車整備士の転職市場には3級や2級の資格を持つ人が多くいますので、付加価値として特殊整備士資格を持っていれば人材としての価値を見出されやすくなり、採用の判断基準として役立つことが多くなるでしょう。
最後に
以上、自動車整備士の基礎知識についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備士の資格取得に実務経験は必要?3級・2級について解説!も一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。