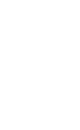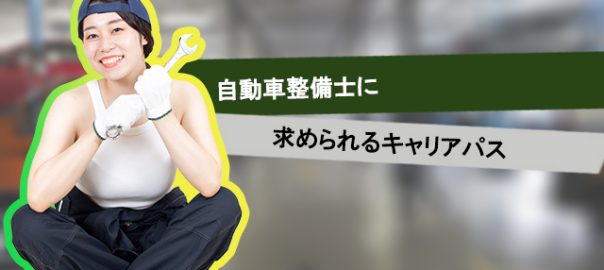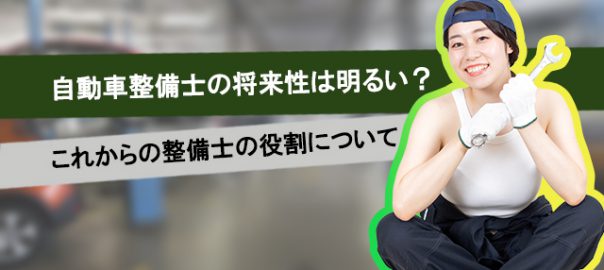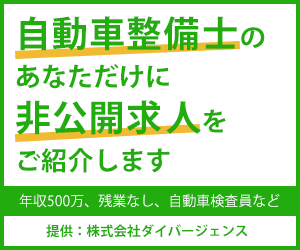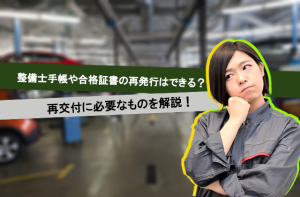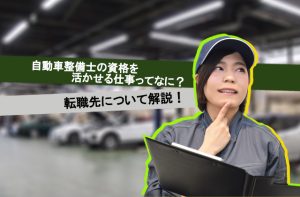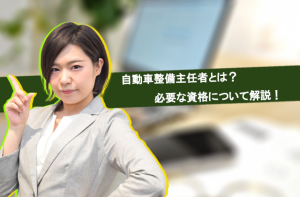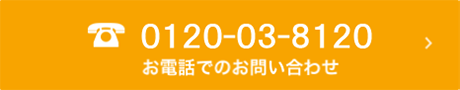そもそもキャリアパスって?

求人情報や企業の採用面接などで使われる専門用語に『キャリアパス』という用語があります。このキャリアパスという用語、意味をきちんと理解せずに聞き流している方も多いでしょう。
キャリアパスとは「ある職位や職務に就任するために必要な業務経験とその順序、配置移動のルート」の総称です。もっとカンタンに分かりやすく言えば「キャリアアップの道筋」です。キャリアパスが明確であれば、この仕事を5年続けていけば、資格を取得して上位のポストに就けるなどの自分の将来像を描きやすくなるでしょう。目指すキャリアに辿りつくために必要なスキルなども分かりやすくなります。
無資格・未経験からのキャリアパスの一例
例えば、無資格・未経験で整備士業界に就職した場合のキャリアパスの例を見てみましょう。
まず、実践経験を積んで1年後に3級整備士資格を取得し、その3年後に2級整備士資格を取得します。その後、有資格者として整備主任者に就任し、さらに1年の実務経験を積んで自動車検査員の資格を取得、10年後にはマネージャーなどの管理者になることができるとしましょう。
このようにルートが明確だと、社員にとっては「4年後には班のリーダーになるんだな」「10年後に資格を取れば管理職になれるけど、現場からは離れたくないな」など、その企業で働く上でのビジョンが明確化します。
キャリアパスは、働き手にとっての道しるべであると同時に、企業にとっては社員のモチベーションを向上させるアイテムでもあるわけです。
自動車整備士は結婚出来ない?整備士の出会い事情も解説!
自動車整備士に求められるキャリアパスは?
全くの未経験から自動車整備士としてスタートすると、まずは3級自動車整備士を目指すことになります。3級取得後3年以上の実務経験を積んだら2級整備士の資格を目指しましょう。
2級整備士を取得すれば、ほとんどの自動車整備ができるようになります。整備士としての道を究めるにしろ、マネジメントの道に進むにしろ、キャリアアップしていくにあたって2級整備士以上の資格が求められます。
さらに3年の実務経験を経るか、専門学校の1級整備課程を修了した場合、1級整備士の取得を目指すことが可能です。
1級整備士になればより高度な自動車整備も可能になります。1級整備士を取得すれば、自分自身のスキルが高く評価されるだけでなく、整備工場においての安全管理や後輩整備士のリーダーとして働くことになるでしょう。
こうして自動車整備士としての現場作業を経験した後は、フロントマネージャーやフロントアドバイザーなどのフロント業務に異動となることもあります。お客さまと自動車整備士をつなぐ橋渡し役として、受付や診断、見積り、発注などの接客や事務仕事を受け持つことになります。
自動車整備士のキャリアパスは整備士資格の等級によって明確化されているので、目指すキャリアに必要な資格取得を目指して頑張りましょう!
自動車整備士の将来性は明るい?これからの整備士の役割について
最後に
以上、自動車整備士に求められるキャリアパスについてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備士になるための勉強の仕方とは?独学の方法を解説!も一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。
自動車整備士の需要はなくなる?

ここ最近の自動車の技術革新は目覚ましいものがあります。環境に配慮したハイブリッド自動車や電気自動車は、いまや珍しいものではなくなりました。交通事故を防ぐための安全装置も発達し、衝突回避のブレーキアシスト装置は軽自動車にまで装備されています。
海外では完全自動運転の自動車が公道でテスト走行をするなど、安全装置はどんどん進化しています。今後、自動車整備士の仕事はなくなってしまうのでしょうか?いいえ、決してそうではありません。
どれほど技術が進化しても、機械に故障はつきものです。また、故障を防ぐためには点検・整備も不可欠となります。いくら自動車が進化を遂げていても、必ず「故障、修理、点検・整備」というサイクルが存在し続けます。
このサイクルの中心的存在となるのが自動車整備士で、それはいくら自動車が進化し続けても変わりありません。そのため、今後も自動車が存在し続ける限り、自動車整備士は必要とされるのです。
今後の整備士に求められる役割
時代が変わっていくにつれ、自動車整備士に求められる役割は変わっていきます。自動運転が一般化し、技術の進歩により車が丈夫になるにつれ、車は壊れにくくなり、今以上に事故や故障を防ぐための点検整備や車検の割合が増えていくでしょう。
また、技術的には電気自動車や電子制御装置などを整備・修理する技術が求められていきます。
将来性のある自動車整備士になるには?

自動車整備士として永く生き残るためには、自動車に関する幅広い知識と技術が必要不可欠です。故障部分を的確に判断し修理ができるというのは自動車整備士として最低限求められるスキルですが、自動車の進化に伴い、新しい技術のエンジン、電装部品なども増えています。
機械に変化があれば、使用する工具や技術も変化してきます。こういった「時代の風」をしっかりと感じ取りながら、どんな自動車でも修理、点検・整備ができる自動車整備士は将来性があると言えるでしょう。大切なのは向上心、そして探求心です。新技術の研修などがあれば、積極的に参加しましょう。
身に着けるべきスキルはある?
先ほど、安全装置の進化についても触れましたが、これからの時代はなるべくコンピューターに強い自動車整備士のほうが、より将来性が期待できます。電子制御装置関連の整備技術を向上させたり、電気自動車等の整備の業務に係る特別教育などを受講しておくといいでしょう。
また、自動車整備士はただ自動車を修理、点検・整備していればいいという仕事ではありません。自動車のオーナーに対して、故障部分とその原因、修理内容、今後故障を起こさないための「自動車整備士ならではのアドバイス」を丁寧かつ分かりやすく説明する必要があります。
修理した自動車が再び故障しないためのアドバイスができれば、自動車のオーナーからの厚い信頼を得ることができるでしょう。そのためには、コミュニケーション能力も非常に重要です。
自動車整備士として海外で働くには?海外移住はできる?
最後に
以上、自動車整備士の需要と将来性についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備士に向いている人とは?適正を知ろう!も一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。
知識や技術面の成長

自動車整備士の資格を取得していると、既に自動車整備についての基礎的な知識は身についているでしょう。
しかし、資格を持っていても、学校で勉強することと現場での仕事は勝手が違います。学んできたことが通用せず、最初のうちはミスしてしまうことやできない仕事が多いかもしれません。
そこで足を踏ん張って、地道に努力を積み重ねていくことで、できる仕事はどんどん増えていくでしょう。整備士として働くことで、より実践的で役に立つ知識や技術をたくさん得ることができます。
そうして以前できなかった整備ができるようになったり、難易度の高い整備を完璧にこなせるようになったとき、整備士としての大きな成長を感じられるでしょう。
部下や後輩を持ったとき
部下や後輩を持つことでも、自分の成長を感じられるでしょう。ある程度の現場経験を積むと、人の上に立つ立場となり、部下や後輩の面倒をみることになります。
部下や後輩に的確な指示をするためには、自分の手元だけでなく現場全体の流れを把握し、さらに部下のレベルについても考慮する必要があります。また、わからないことがあればわかりやすく教えてあげたり、部下のミスをフォローする場面も出てくるでしょう。
自分が転職したばかりの頃に教えてもらったこと、わからなかったことを自分が部下や後輩に教えることができると、成長を感じられるでしょう。また、人に教えること自体もさらなる自分の成長に繋がります。
さらに、部下や後輩が成長すると自分の業務が楽になります。そして、その分、これまでできなかったことにチャレンジできる時間と、精神的な余裕が出てくるのです。
部下や後輩を持ちたくないという人も中にはいますが、相手を育てることは自分自信の成長に繋がるということを忘れてはなりません。お互いにお互いを成長させあうことで、更なる高みを目指せるでしょう。
日々の仕事の中でギャップを感じ、整備士という仕事を苦しく思う時期もあるかもしれませんが、周りの人に支えてもらい、また周りを支えながら成長を実感していきましょう。
整備士はどんどん成長できるやりがいある仕事!

国内外に自動車の種類は無数にあり、それに使われる技術は進歩し続けています。そのため、整備の仕事は新しい刺激に事欠かず、成長しようとすればいくらでも新しい知識や技術を身に着けることができます。
近年の整備業界は特に、大きな変革期を迎えており、目覚ましく技術が進歩し続けています。成長意欲の強い方には、非常におすすめの職業です。
最後に
以上、自動車整備士が成長を感じる場面についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備士になると得られるメリットについても一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。