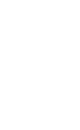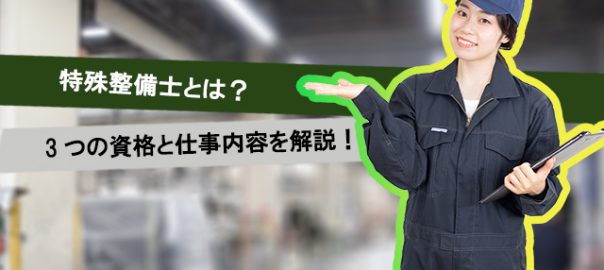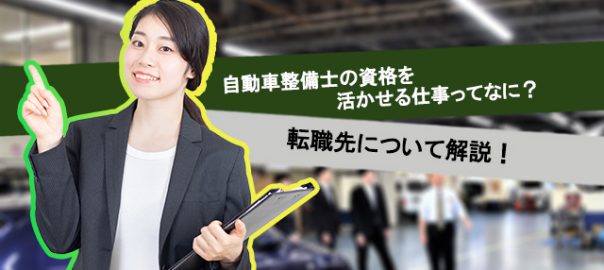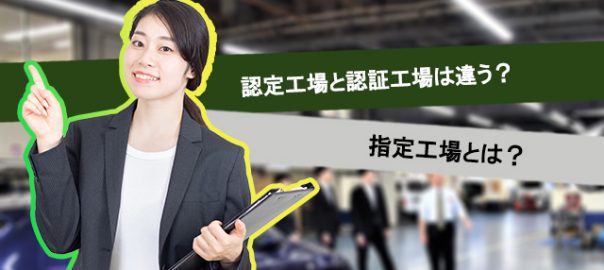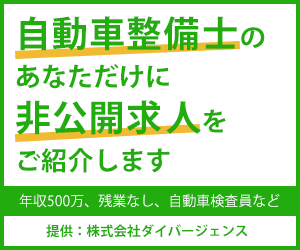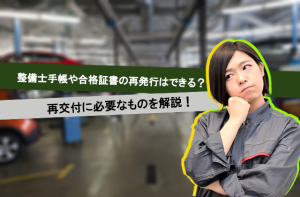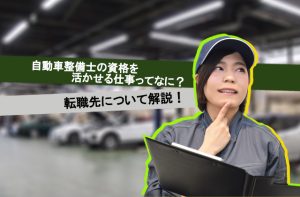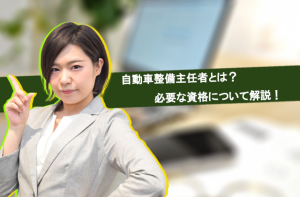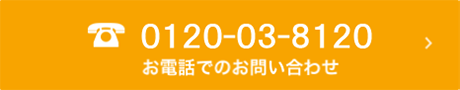特殊整備士はどんな資格?

一般的に、自動車関連の専門学校等を卒業した方が取得しているのは2級整備士です。自動車関係の学校を卒業していない方は実務経験を積みながら、3級整備士・2級整備士とステップアップして整備の仕事を行っていく流れになります。
自動車整備士資格について詳しく知りたい方は、自動車整備士の種類をご覧ください。
整備士資格の中でも特殊整備士の資格は、整備の仕事をしていく上で、絶対に必要な資格というわけではありません。しかし、資格を持っていることで就職が有利になったり、より知識が豊富になるため、お客様に安心と信頼感を持ってもらうことができるようになります。
特殊整備士の中には3つの種類の資格があります。
自動車電気装置整備士
自動車電気装置整備士は、自動車の電気装置部分(電子制御装置、バッテリー、冷暖房装置などの装置)の点検・修理・整備などを行います。電気システムに特化した、専門的な知識や技能を持つスペシャリスト資格です。
自動車の電気装置の整備自体は、2級整備士であっても対応ができます。しかし、電気装置整備士の資格を取得することで、電気回路などについてのより深い知識が手に入ります。現在の自動車はハイブリット車や電気自動車などでなくとも、電子制御で動いている車が多いため、近年需要が高まっている資格です。
自動車車体整備士
自動車車体整備士は、自動車のフレームやボディ部分の点検・修理・整備などを行う、自動車の車体に関する専門的な知識や技術を持ったスペシャリストの資格です。
車体整備士は、主に自動車の鈑金塗装をする際に役に立つ資格になります。鈑金塗装そのものは無資格で行うことが可能です。
しかし、仕事内容は職人的な要素が強く、経験や整備した台数がモノをいう仕事になります。それでは、資格は意味の無いものかというと、それは間違いです。「資格」という形で技術や知識を証明できる目に見えるものがあることで、職場や顧客から信頼を得ることが可能です。
自動車タイヤ整備士
自動車のタイヤ点検・修理・整備などを行う、タイヤの専門的な知識や技術を持つことを証明する資格です。平成12年に行われて以来、現在まで国家試験が行われておらず、試験再開は未定となっています。取得を目指す方は、いつ試験が再開されてもいいように実務経験を積んでおきましょう。
特殊整備士の受験資格・条件

特殊整備士の資格は、誰でも取得できるわけではありません。資格取得のためには、2つのステップがあります。
1.受験資格を満たす
まずは、試験を受験するために、
・特殊整備士の養成校を卒業する
・自動車整備系の学校を卒業後、実務経験1年以上
・実務経験2年以上
いずれかの条件を満たす必要があります。
2.学科試験・実技試験に合格する
整備士資格は国家資格であり、取得するには学科試験と実技試験に合格する必要があります。
試験は、「国土交通省が行う自動車整備士技能検定試験」と「国土交通大臣の登録を受けた実施機関(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)が行う自動車整備技能登録試験」の2つがあり、いずれか1つに合格することで資格を取得できます。
特殊整備士を取得するメリットは?

特殊整備士は、整備をするときに必須の資格ではないため、単体で取得しても就職や仕事をするときにあまり意味をなしません。自動車整備士2級や3級を持った上で取得している場合は、就職時に高く評価され、任せられる仕事の幅も広がっていくでしょう。
整備工場に一定の人数の特殊整備士の資格を持っている方がいる場合、設備等の条件を満たし運輸局の審査に合格する必要がありますが、国から「優良自動車整備事業者」という認定を受けることができます。資格を持っていれば、この認定を受けた事業者から求められやすくなるメリットがあります。
自動車整備士の資格を取得している、あるいはこれから目指すのであれば、得意とする分野をはっきりさせるにあたって特殊整備士の資格を取得する意味は大きいです。特殊整備士を取得すれば仕事の幅が広がり、就職活動を有利に進められる可能性が高まります。
最後に
以上、特殊整備士の仕事内容や3つの資格についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、3級自動車整備士の資格も一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。