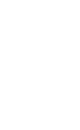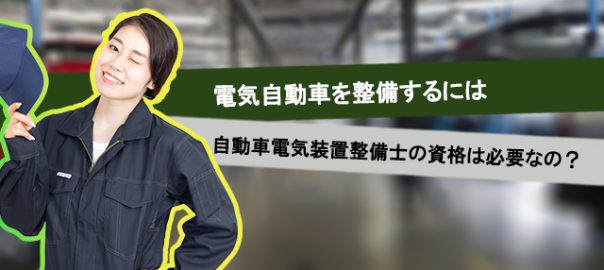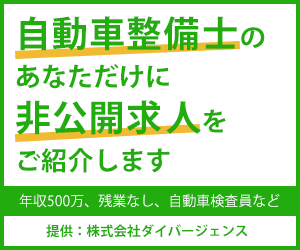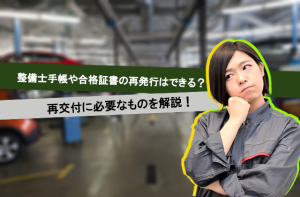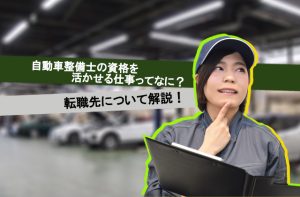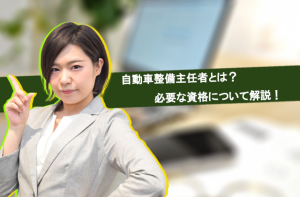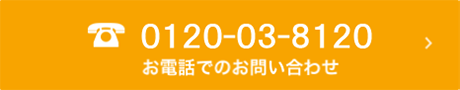自動車整備士のキャリアプラン

整備士の転職を考えている人は、どのようなキャリアを積んでいくのかを知っておくと良いでしょう。会社によって異なりますが、一般的な自動車ディーラーに入社した自動車整備士のキャリアは、新人研修から始まることになります。
新人期~中堅期
新人期から中堅期は、整備士としての基礎を築く重要な時期になります。
新人研修は、多くは1週間から3ヶ月程度の期間が設けられ、マナーや社内ルールなどについて教えられます。研修後は先輩や上司に習いながら、オイル交換やタイヤ交換などの軽作業を行い、その後は先輩と一緒に定期点検作業などをします。半年ほどで整備車両を一人で動かすことを認められることが多く、引取納車などを任されるようになります。
このように作業をしながら実践的な知識や技術を身につけていき、1年ほどで一通りの定期点検ができるようになり、その後、車検整備などを覚えていくことになります。3年以上実務経験を積んでいくと、自動車整備士として知識や技術がひと通り身につき、後輩への指導や、お客様への対応をするフロント業務に従事する人もいます。
中堅期に差し掛かってくると、人によっては整備主任者や自動車検査員として活躍する人も出てくるでしょう。
整備士ベテラン期からのキャリアアッププラン

10年、20年と勤務していくと、整備技術全般に精通し、現場の業務を全て一人でこなせるようになります。そうなると、目標管理や業態管理などの管理業務や、人事や教育などのマネジメント業務に従事するケースが多くなります。
整備士から昇格してマネージャーや工場長などになったり、整備士としての経験を活かして営業部へ異動する人もいます。また、自動車整備士としてのノウハウを身につけ、独立して整備工場を開業するという道を選ぶ人が出るのもこの時期です。
スキルを身に着けてキャリアアップし、転職することで給料などの待遇を向上させるという選択肢もあるでしょう。転職先には、そのまま自動車整備士として働く以外にも、保険会社のアジャスターやカー用品店、建設機械メーカー、大手運送会社など、自動車整備士としてのスキルを生かせる様々なものがあります。
自動車整備士として転職する人は、将来的にどのようになりたいのかを考えながら職場を選ぶと良いでしょう。どのようなキャリアパスがあるのか、面接などのときに聞いてみると将来を想像しやすいかもしれません。
最後に
以上、自動車整備士のキャリアについてご紹介しました。この記事を読まれた方は、3級自動車整備士の資格も一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。